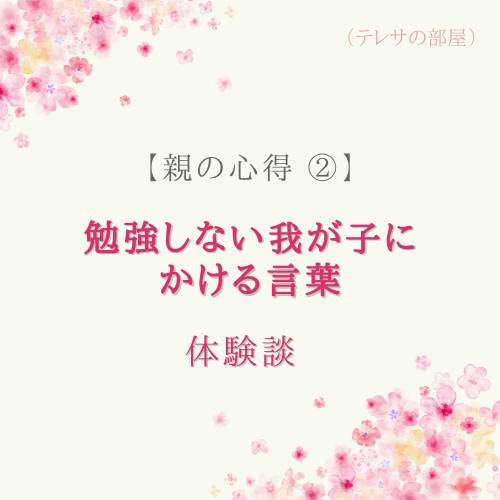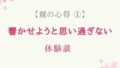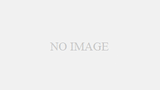テストが近いというのにゲームをしている姿、スマホを見ている姿、だらだらしている姿、そんな我が子が目に入ると、どうしても心がザワザワするものですよね。
「もうすぐテストなのに勉強しなくていいの?」
状況は悪化するだけだと分かっているのに、堪えることができずかけてしまうこの言葉。
予想通り、言い争いへと発展…
苛立った子どもが「よし!勉強するぞ!」となるわけもなく、結局はなにも得ることのないまま、ただただ状況が悪化してしまったというお話をよく聞きます。
では、親が口を出さなければ勉強を始めるのでしょうか?
私は、そらまるによって気づかされました。
勉強するかしないかは、親が口を出すか出さないかの問題ではなく「その子自身がテストに対してどう向き合っているか」なのではないでしょうか。
我が子にとってテストとは?
「1つ1つのテストが内申に反映し、その内申点よって行ける高校が決まる」
まず、この意識がある子は「内申を取って〇〇高校に行きたい」というテストへ向き合う理由があります。
テストの結果を友達と常に競争している子も「友達に勝ちたい」というテストへ向き合う理由があります。
しかし、テスト前なのに勉強しない子には、この「テストへ向き合う理由がない」のです。理由もないのに勉強なんてしたくないわけです。
大人たちは口を揃えて「内申の大切さ、それによって行ける高校が決まる、大学が決まる、将来が決まる、だから常にテストは頑張らないといけない」と伝えています。
それでも、それを理由とはできないのです。
そんな先のことを理由として頑張れない、そんな先のことを自分事に捉えられないのです。
「すでにテストを頑張る理由を持っている子」と「まだテストを頑張る理由を見いだせていない子」この両者に「テストを自分事と捉えて頑張ること」を望むことは、後者の親子にとっては苦しみを生むだけなのです。
では、「まだテストを頑張る理由を見出だせていない子」に、親としてどう関われば良いのでしょうか。
個性を受容すること
そもそも、「テストへ対しての意味を見いだせていない」ので、「勉強しなさい」という声掛けは通用しないのです。
この声掛けは、ただ「親子間で険悪なムードとなり状況悪化への入り口」となるだけなのです。
では、どうしたらいいのか。
「勉強に対して声をかけない」ということです。
「そんなこと分かっている!でもそれができない!」
そのお気持ちは「ノー勉そらまる」を育ててきた母であるからこそ、痛いほどお察しできます。
私が言いたいのは「勉強に対して」という部分です。
「勉強に全く関係ない話」だけを話していたらいいのです。特別な話など必要はなく「本当に他愛のない話」をしていたらいいのです。
テレビを見ながら「この人最近よく見かけるけど人気あるの?」とか、学校から帰宅したら「今日のお弁当美味しかった?」とか。
そして塾から帰宅したら「おつかれさまー。疲れたでしょう。お風呂とご飯どっち先にする?」とだけ声をかける。
このように、「勉強に関係ない話」だけをしていると、子どもにとって家が居心地の良い場所となっていきます。
そして「勉強に関係ない話」だけをしていると「言い争いになる種」がなくなり、親子関係が良くなります。
親子関係が良くなったとき、色々な話ができるようになります。なぜなら子どもが親に対して心を開いている状態だからです。
その状態となったら伝えてあげてほしいのが、その子の個性や武器です。
ここでは、あえて長所でなく個性と書いています。
ときどき「良いところなど思いつかない」というママがいます。
深く聞いてみると優しい、素直、真面目、努力家(コツコツ型)というような一般的に良しとされていることが長所であり、これらの逆であると短所と捉えているようでした。
はたしてそうでしょうか?
反抗的、頑固、適当、効率重視(コツコツ型ではない)など、こういった特徴は扱いにくいとされるだけであり、一般的でない、型にハマらない、ユニークといった個性的であることが武器だと私は思っています。
扱いにくいうことは自分軸を持っていると捉えますし、そして他人より自分の意思を1番大事にできるのだという意味で安心でもあります。
どちらが長所どちらが短所でなく、全てが個性であるわけです。
我が子を変えよう、正そうとするのではなく「そのままでいい」と親が受容していると、子どもは自分の個性に自信を持ち、そして進む方向が見えはじめるのです。
「勉強する理由」とは、そこから見つかっていくのではないでしょうか。
勉強面での強み
そして、ここで大事なのが塾との連携です。
塾の先生は勉強のプロです。そのプロから我が子の勉強面での特徴や強みを聞き、共有しておくのです。
そして我が子に伝えるチャンスがきたとき、個性の話と共に「先生がこう言っていたよ」と強みを話して聞かせるのです。
私は、そらまるに「数学にキラリと光るものがあるから、あとは定着さえ怠らなければ早慶を狙える子ですって先生が言ってたよ!」とか「そらまるは、英語も数学もざっくり読む力が強くて、それは早慶に絶対必要な力なんだって!良かったね!」などと、隙あらば伝えていました。
もちろん、先生からはそれ以外のたくさんのダメ出しも頂いていました。
例えば、「ざっくり読む力は強いが、1つ1つきちんと読まねばならないものについては本当に弱い」と言われてもいましたが、そんな部分は省いてそらまるの強みの部分だけを伝えていました。
自分の個性を認められ、それが人生においての武器だと伝えられ、そのあと勉強面での強みを伝えられたら、気分の悪い子なんていないのではないでしょうか。
「それらを生かして、なにかをどこかを目指してみないか?」という話に結びつきやすくなるわけです。
ただし、ここで早急にその子の行動や結果を求めてはいけません。
すぐに言葉で伝えたり行動に移す子もいれば、自分の頭の中でじっくり温め自分のタイミングで行動する子もいるのです。
我が家がお世話になった家庭教師の早田先生は「なぜ男の子は、私の前では素直で優しいのに、お母さんにはあんなにぶっきらぼうになるんでしょう?(笑)」と仰っていましたし、高校でお世話になった家庭教師の高尾先生は「言葉数の少ない子のほうが実は頭の中で色んなこと考えているんです。聞いてみたら本当に驚きますよ。まあお母さんには話さないんでしょうけどね(笑)」と仰っていました。
たしかに、言葉で伝えてくれたら親としては分かりやすく安心できますが、言葉に出さない子も頭の中では実は色んなことを考えていて、そして行動に移すのも自分のタイミングなのです。
目で見えないこと、耳に聞こえないことで「この子は何も考えてない」と決めつけてイライラしてしまうときがあったら、その時は我が子を問いただすのではなく、まず自分の中の「信じる気持ち」を見つめ直すことが最優先なのです。
親は、全ての答えや安心を外に(我が子の行動に)求めがちですが、実は安心を得るための全ては内側に(自分自身の心を整えること)あるのです。