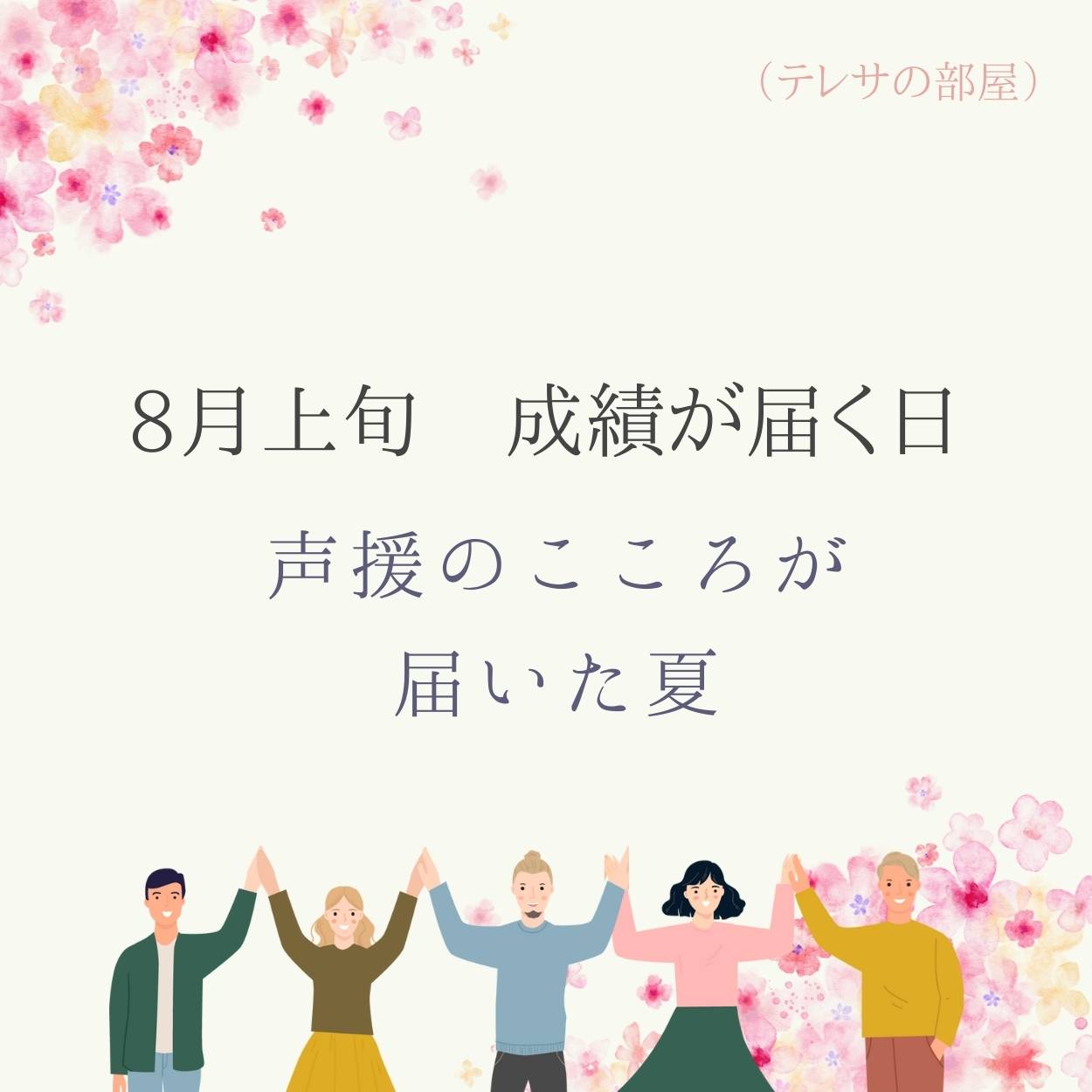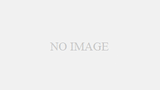8月上旬、慶應義塾高校の成績が郵便受けに届きます。
この成績表を待つご家庭の心持には雲泥の差があります。
中間・期末とどの教科も平均点以上を取れていたご家庭は期待に胸を膨らませ、
中間が悪くても期末でなんとか盛り返したご家庭はそれなりに安心した気持ち。
しかし、どちらも成績不振だったご家庭は…
まるで地獄からの手紙を待つように、不安と恐怖の時間を過ごしているのです。
成績安定組から届いたメッセージ
私のもとにも、ぞくぞくと成績のご連絡をいただいております。
「テレサさんにアドバイスを頂かなければ、私はきっと中間テストで取れなかった原因を根掘り葉掘り聞いたり、期末対策に余計な口を出してしまっていたと思います。息子は、期末でお友達に過去問を共有させてもらったり対策できたようで盛り返せました」
「テレサさんの予想通り、成績は8を超えていました。今回の成績を受けて学部説明会にも行ってみようと言っており、親が声をかけなくてもこうして自分で動機が生まれていくのですね」
「テレサさんのアドバイスで目が覚めました。「もっと上位を目指してほしい、この学部のほうがあなたに合っているし将来にも繋がるよ」など親の想いや理想を子供にぶつけることは子供をコントロールしていることに繋がる。「今、我が子がやりたいことをただ楽しんでいる」その積み重ねがその子の人生になる、本当にその通りですね。」
その他にも、ポジノー勉読者の方から今回の成績にホッと一安心の内容のメッセージを頂きましたが、どのメッセージにも共通しているのは
★★「親として見守る姿勢を保てた」「子供の成長を感じることができた」★★ということです。
成績不振のときにも同じことができるか
こうした「見守る姿勢」「口出しを控える」「行動変化に注目する」は、
成績に不安の無いときや、子供が成績不振を自分事として受け止め行動している姿が見て取れるときには、比較的容易にできます。
しかしーー
成績不振のとき、それでも我が子が全く自分事に捉えていないとき。
その状況で同じことを貫けるかどうか。
ここにこそ、親の覚悟が問われます。
今、まさに成績不振で孤独と不安の中にいるお母さんへ
数年前の8月、私はまさにあなたと同じでした。
6月の保護者会では、わが家のみが担任から面談で残され、そして8月に地獄の成績が届きました。
学校に知り合いが一人もいなかったこの時期、誰にもこの気持ちを吐露することができず、更にそらまるはそんな状況下でも勉強をすることは1日もなく…私は1人不安の奈落の底にいました。
そんな私だからこそ、孤独を感じているお母さんへ向けて、ポジノー勉というこのブログを書いています。
まず1番にお伝えしたいことは、私はどんな状況でもそらまるを絶対に馬鹿にしなかったということです。成績不振だからってその人間性までを否定するような言葉を浴びせていいわけはないのです。
どんなに辛くても、親子の関係に甘えた言葉の暴力だけは与えないと、ぜひ誓って頂きたいのです。
今絶望の中にいる(と思っている)お母さん。
あなたは応援団長です。成績など関係ないのです。
我が子が健やかなるときであろうと病めるときであろうと、あなたはどんなときでも1番の応援団長なのです。
一歩を踏み出してみませんか?
あなたの抱えている思いを聞かせてください。
心が軽くなれば、明日からのあなたはきっと変わります。
※ボタンを押すと、公式LINEから無料でお話ができます。
夏休み、まずは「家庭を明るく」
成績不振の子は、一見親から見て何も気にしていないように見えるかもしれません。勉強にも取り組まずゲームばかりしていたり、友達と遊んでばかりいたりします。
しかし、実はメンタルはすり減っています。
「留年」という文字が常にちらつき、不安の中にいます。
実際は、何をどうしたらいいか分からない、どうしてもやる気が出ない、そういった中で現実逃避をしている状況なのです。
この夏休み、例えば家族旅行を計画しませんか?たとえば、おいしいものを食べに連れ出しませんか?
この時期に大切なのは「ゲームを禁止したり勉強だけをさせる夏休み」とするのではなく、まずは、家庭を明るく・気楽に保つことが最優先です。
家庭内が成績不振を気に病み、重苦しい雰囲気を醸し、本人の時間を縛ったところでなにもいいことはありません。
慶應義塾高校は、夏休みに予習復習をすれば2学期のテストに直結するというものでもありませんし、成績不振の子にはまず心の元気を取り戻すことが最優先だと考えます。
もちろん、自ら勉強したいという意欲の元で予習復習をすることは素晴らしいことです。しかし成績不振の子の頭の中は、まだその状況にはないことがほとんどです。
気分が落ちている時は、やる気もなく、動くのすら億劫になる。
逆に、心が元気なときは、エネルギーが溢れ、頭も体も軽やかに動く。
これって、自分に置き換えてみても同じですよね?
でも、我が子が成績不振であるという現実を目の前にすると、親はこの「人としての当たり前の流れ」を、つい忘れてしまいがちなのです。
子供だって「ひとりの人間」なのです。
「好きなことを学ぶ」夏
そらまるは、2回目の1年生となったと同時に家庭教師の先生を週2回お願いしました。(※以下、高尾先生とします)
1学期も成績不振のままでしたので「夏休みは、高尾先生にたくさん入って頂き、予習復習をしてもらおう」と提案した私に、そらまるは真逆なことを告げました。
「予習復習とかしても塾高の2学期のテストには意味ないから、夏休み中は高尾先生は断って。もし勝手にお願いしても、僕は絶対授業受けないから」
1度言ったらテコでも動かないそらまるです。私は、面食らいながらこのことを高尾先生にそのままぶつけると、高尾先生は即答されました。「そらまる君の言う通りです」と。
そして、こう続けられたのです。「そのうえで僕に任せてもらえませんか?」
7月半ば、我が家で1学期最後の授業を終えた高尾先生がなにやらそらまると2人で言葉を交わしていました。玄関を出るとすぐにそのやりとりをLINEで報告してくださいました。
あれだけ「予習復習は意味がないから夏休み中は高尾先生を呼ぶな」と言っていたそらまるでしたが、高尾先生いわく「3分で話はまとまりました笑」とのことでした。
以下、そのとき頂いた高尾先生からのLINEです。
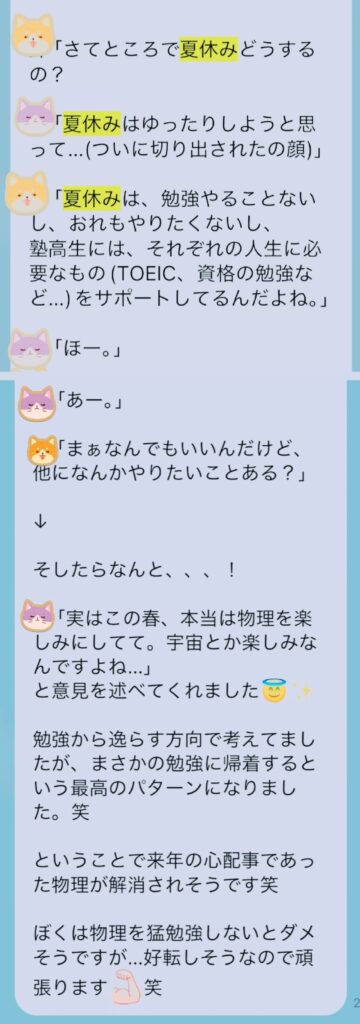
これは、高尾先生がそらまると3分だけ話したやりとりをそのまま私に送ってくれたLINEです。
内容は一部を抜粋して短くまとめています。当時のそらまるは、学校の成績をどうやって取るのか、なぜ取る必要があるのかーーあらゆる「当たり前」がどうしても腑に落ちていませんでした。
高尾先生は、その「親や学校の先生、友人達にはどうしても届かなかったそらまるの壁(動かない視点・自分なりの価値観の枠組み)」に寄り添いながらその突破口を探し、一歩を踏み出すきっかけを与えてださったのです。
原級が確定し留年の意向を伝えに学校へ出向いたあの日から、そらまるが私や担任には一言も漏らしていない胸の内を、高尾先生には話していました。
「進級できないことで1番辛かったのは、2年から始まる物理をずっと楽しみにしていたのに、それを学べないことです。」
高尾先生は文系の先生でしたが、そらまるに物理で何を聞かれても答えられるようにと猛勉強してくださいました。
あるとき、家に入る前のエントランスで教科書をじっと見ている先生とバッタリ遭遇しました。
「そらまる君は、重箱の隅をつつくような鋭い質問を飛ばしてくるんですよ。
僕がそれに答えられないとそらまる君の目からの信用の光が消えるのが分かるので、絶対に答えられるように必死で最終チェックしてたとこです(笑)
この物理の時間は、そらまる君と僕の戦いです!(笑)」
こうして全力で支えてくださった高尾先生に出会えたことで、今のそらまるがいます。そらまるを育てるうえで、周りにはいつも協力してくれる大人たちがいました。
その存在がどれほど大きな支えであるか、私は身をもって知っています。
そらまるは、「物理」という学びたかったものを学ぶ夏休みで心の元気を取り戻していきました。
心が元気なら、子供は動き出す
この夏休みをきっかけに、2学期が始まるとすぐにそらまるの意識に変化が起きたことに、私は驚きました。そらまるは「テストで成績を取る」ということに、ここでついに初めて意識を向けるようになったのです。
高尾先生伴走のもと「授業への向き合い方」と「テスト対策の取り組み方」に、だいぶ向き合うようになり、そして無事2年生に進級したのです。
2年生になると「もう自分でテスト対策はできる」と言って高尾先生と離れ、そこからそらまるの自走が始まりました。
しかし、そらまるは高校時代最後まで、友達と過去問を共有しあったり、授業内容からお互い問題を予想しあって一緒に勉強するという1番効果的で一般的な勉強の仕方はせずに、1人でテスト対策に取り組むというスタイルは崩しませんでした。
自分のスタイルを崩さないそらまるは、やはりその後も成績に山あり谷ありはありヒヤヒヤさせられるときもありましたが「谷になったら次で挽回する」というようなテスト結果を自分事に捉えての行動を考えられるようになりました。
親としては、このような不器用な部分のあるそらまるに歯がゆさを感じることは多かったですが、本人のやり方を尊重し、谷に落ちたときにも口は出さずにただ応援し続けました。
そんなそらまるですが、大学に進学してからは同じ学部のクラスメイトたちと学校が閉館するまで一緒に勉強し情報を交換しあっています。こうして子供は自分で変わっていくのだなあと実感したものでした。
子供が自分で動き始めるのは「心が元気」なときです。
その心を元気にするのは「安心できて自由でいられる家庭」
そして、その家庭には、どんなときでも見守る応援団長ーーお母さんがいます。
あなたの今の状況をお聞かせください。
- ⭐ 見守るは伝わる
- ⭐ 悔し泣きしながら車を走らせた母
- ⭐ 地獄の保護社会